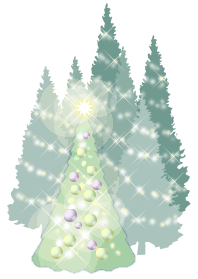
(3)
二人はとりあえず、お互いどのようにしてこの場所へやってきたのかを簡単に教え合い、建物の中を探索し始めた。
「ふーん、妹にプレゼント、ね」
「ガイルくんも、僕とそんなにかわらなさそうなのに、その・・・・ステンレス?さんの借金払わなくちゃならないなんて、大変だね」
「あのバカいっつも肝心なときにいなくなりやがって・・・・っ」
建物は、二人が倒れていたホールを中心に、ちょうど左右対称の構造をしているらしかった。ホールの右手に見えた扉を抜け、道なりに廊下を進んでいき途中二つほど部屋を抜けた後、最初のホールの左手側の扉から戻ってきてしまった。
他にもどこか、通路はないかとホールを調べていた二人は、薄暗い中でなんとか、先ほどの左右の扉とは感触の違う、石で出来た両開きの扉を見つけた。四角いホールをぐるりと円形に囲んでいる、妙なオブジェたちの陰に隠れていて、見えなかったのだ。
「これ、どこに通じてるんだろ?」
「開けてみれば分かるだろ・・・・って、固! おいハヤト、お前も押せ」
「うん」
二人は取っ手を押さえながら、それぞれの扉に肩を押し当て、必死に力を込めた。ずるずるとタイルの上を靴が滑り、二十分ほどそれをくり返してすっかり息が上がってしまった。
「っはぁ・・・・はぁ、くそ、剣があれば、まだなんとかなったのに!」
「剣が使えるの? ねぇ、どんな剣!?」
「あ? いや、まだ子どもだし、腕もそんなに長くないから、今のところは男用の二番目に小さいサイズのロングソード・・・・って、別にいいだろそんなこと!」
「ロングソードかぁ、かっこいいね!」
「かっこいい、か?」
ガイルの顔に、複雑そうな、陰りのある表情が浮かんだ。しかし、ファンタジーという『夢』の世界にあこがれを持つ隼人は、それに気付かないままはしゃぎ続ける。
「だって、僕の世界じゃそういうのを、本当にゲームの中でしか扱えないし、かっこいいって思っても実際家の外に刃物を持っていったら、捕まっちゃうし」
「捕まるのか、お前の国では」
「うん、決められたのより長い刃物と、鉄砲を持つのはダメって」
「・・・・へぇ」
とん、と開かない扉に背を預けて、ガイルは隼人をすっと見据えて、腕を組みながら言った。
「いいじゃないか」
「え?」
「剣だの、銃だの、そんなもの普通に暮らしてる人間が、持ち歩くものじゃないんだからな。あと」
ガイルの双眸が、スッと細められる。氷のように冷たい青天の色をした瞳が、きょとんとした表情の隼人を見据えた。
「剣を持ってるだけで、かっこいいなんて軽々しく言うな」
「・・・・? うん、わかった」
「わかってないだろ」
「・・・・うん」
盛大に、どはぁーとため息をついて、ガイルはちょいちょいと手招きをした。
にこにこと笑って素直にガイルに近づいていった隼人だが、すぐ隣に立ち止まった瞬間、べちっとデコピンされた。
「痛いよ」
「そりゃな。・・・・いいかハヤト、俺とお前は違う世界の住人だ。価値観も違うだろう。だが考えてみろ。お前の目の前に正体不明の人間が、なんでもいい、刃物を持って歩いていたり、自分に向かって近づいてきたりしたら、どう思う」
「え・・・・ちょっと怖い、かな」
「かっこいい、なんて思うか?」
額を押さえる隼人は、ガイルの言葉に目を瞬かせた。
「お前の母親とか知り合いとかが、家の中で包丁持ってるのは料理をするためであって、自分に危険はない。それで・・・・お前の世界で、ロングソードが存在するのは何かのゲームの中、といったか」
「うん、僕は持ってないけど、友達にちょっと見せてもらったことがあるんだよ。たくさんお話があって、そのお話を、主人公になりきって進めていくんだ」
「それをして、お前自身に危険は及ぶか?」
「ううん、全然」
「・・・・時と、場合と、人間によるということだ。剣でも包丁でも、役に立つこともあれば、人の命を奪うことを容易にさせることもある」
そう言いきって、ガイルはばしっと隼人の頭の上に手をのせた。ぐわっしぐわっしと髪をかきまわして、ふんと鼻で笑う。なんだか腹が立つ仕草でもあったが、実に彼の雰囲気に似合っていて、隼人は反抗することができなかった。
「ま、お前見たとおり俺の世界じゃ箱入り坊ちゃんの典型例だな。一体お前の世界は、どんなことになってるんだか」
「僕が箱入り坊ちゃんだったら、もっとすごい子もいるけどなぁ。いっつもお母さんと一緒なんだよ? 学校にまでずーっと付き添ってくるんだ」
「・・・・赤ん坊じゃあるまいし。てか本当にいるんだ、そんな人間」
ガイルはくすりと笑って、隼人の頭の上から手をどけた。また扉に寄りかかって、ふと何かに気付く。
「どうしたの?」
「いや、なんかこのへんに・・・・?」
しばらく扉の模様に指をすべらせていたガイルだが、ある一点で指を止め、確認するように何度も同じ場所をつついたり撫でたりし始める。
隼人は独り扉に向かい合って、ぶつぶつと何かつぶやいているガイルの背をぼんやりと眺めていた。
と、そこでようやくガイルが振り返る。
「鍵がかかってるんだな。今、鍵穴を見つけた。なんでまたこんな中途半端なとこに」
「え、じゃあこの建物の中、また歩き回って鍵を探さなくちゃいけないの? ものすっごく広いよ!?」
「俺も、なるべくとっととここからおさらばしたいんだがな・・・・せめてヒントぐらいどこかに残しとけよ」
ガイルが心底腹立たしげにつぶやいたあと、さぁっとホールの中の青白い月明かりが、強まった。
二人が同時に天井を見上げると、模様がずいぶんとはっきり見える、薄い紫と蒼い色をした満月が、吹き抜けの硝子天井の向こうで輝いていた。オブジェの影がずれて、開かない扉の細かい模様が、よりはっきりと浮かび上がる。
「・・・・あれ? ねぇ、この扉の模様、なんかそっちのに似てるよ」
と、扉の模様をさっと見た直後、隼人は扉の模様を指さし、ついで、ホールに飾られているオブジェたちを指さした。ガイルも彼の指の示す先を交互に見つめて、目を見開く。
「確かに、そうかもな」
扉に描かれた模様は、まずぐるりと大小二つ、二重の円があり、大きな円の内側と小さな円の外側に区切られた範囲に、ぐるりと奇妙な形のレリーフが彫られていた。よく見れば、確かにそれぞれのレリーフはオブジェと形がそっくりである。
そして、肝心の鍵穴の部分には、ちょうどこの開かない扉と、右手側の廊下への扉との間に位置している、うねる波のようなオブジェのレリーフが彫り込まれていた。
「ね、あの像調べてみよう!」
「あったらマジですげぇ・・・・ていうか、タイミングよすぎないかこの明かり」
とっとと像のもとへ走っていってしまった隼人の背に、小さくため息をつきながら、ガイルもまた彼を追いかけ鍵を探し始めるのだった。
しかし、そうことは簡単には進むわけが無く。
「見つかんないー!」
「・・・・そりゃあ、な」
はしゃぎまわってオブジェを調べていた隼人だったが、今はむくれてオブジェのそばに座り込んでいる。
ガイルはそんな隼人を見て小さくため息をつき、波のオブジェの先端部に手をかけた。
「そんな簡単に見つかるものか。光さえあればあの扉のレリーフを見分けられるんだし、ここからが本番だろ。いちいちむくれるな」
「・・・・なんかガイルの話し方って、すごく大人みたいだなぁ」
「大人にならざるを得なかったからな」
ぼそりと無意識のうちに答えて、やっと気付いたガイルはびくりと肩を震わせた。小さく頭を振って、背後を振り返る。彼の視線のずいぶん下の辺りで、隼人はきょとんとした表情を浮かべながら見上げてきていた。
「なら、ざるを?」
「色々あったんだよ。いい。もう忘れろ」
ガイルは乱暴に言い放って、オブジェの溝につま先をひっかけた。どこもかしこもうねっているので、足場は余りあるほどある。
かちん。
「あ?」
そんな、驚きの確率で。
ガガガガガ
「わっ、わぁ!」
「な、なんだよこれ!?」
隼人の歓声と、ガイルの絶叫が響く。
オブジェが、その石の質感を保ったままうねり始めていた。さぷん、と台座の上で波がくり返し、繰り返しわき起こる。ガイルは、最初のうねりはなんとかかわしたが、不規則に揺れ動く石の波に足をとられ、ひっくり返る。がんっ、と鈍い音がした。
「ガイルくん!」
「て、だ・・・・」
大丈夫だから、お前は離れろ。そう叫びたかった。しかし、目の前の光景に声が潰れる。
ぐぉん、と滑らかで真っ黒な石の波が、ガイルの真上に覆い被さってきた。このままでは、巻き込まれて、押しつぶされる。逃げたい、逃げなければ、死にたくない、死んでしまってはいけない。
黒。
「す、て」
つぶやいた一瞬あとに、強く手を握られた。黒々とした石の壁は、もう目の前にまで迫っている。
がくがくと長い若草色の髪を引っ張られた。痛い。手を離せ。
パッと痛みが消える。代わりに、自分の手を握る力がさらに増した。
どぷん。
素材提供 :My new history