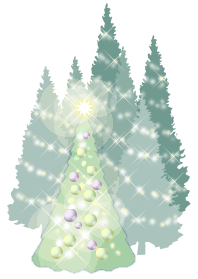
(4)
気付けば、すべてが真っ白だった。先ほどまで石と石の間、その暗闇に身を置いていたはずなのに。
(死んだか)
訳の分からない場所に突然転移してしまって、訳の分からない子どもに出会ってしまって、建物から脱出しようとして突然石の波に呑まれて・・・・。思わず、暗い笑みがこぼれた。
まだ何年と経っていない、あの泥沼の戦いを生き残った・・・・いや、死に損なったというのに、こうもあっさり人間の命は尽きてしまうのか、と。空しくて、頬がぴりぴりして、足が異様に重くて。
「・・・・ん?」
「う、うあー、気持ち悪いよコレ」
ふわふわとあらぬ方向へ漂っていた思考が、一気に引き戻された。最初は薄目で、次に何度かゆっくりと瞬きをして、最後は限界まで見開く。
しゃりっ
ガイルは、雪の降り積もった地面の上でうつぶせに倒れていた。そりゃ頬も手も首筋もじんじんと痺れるような感覚に襲われているわけで。
「おい、どけろ」
「あ、ガイルくん目が覚めたの」
ちょうどガイルの膝裏あたりに腹をのせ、同じくうつぶせのままバタバタと雪をいじっていた隼人は、ぱっと素早く起き上がった。へらっと気の抜けた笑みを浮かべて、真っ赤になった手を差し出す。
「なんか、外に出れたみたいだね!」
「まさか、あのオブジェに鍵があるんじゃなくて、あのオブジェ自体が出口だったってことか?」
ざっと辺りを眺めてみれば、二人の倒れ伏していた場所のちょうど真後ろに、おそらくあの両開きの扉と思われるものを中心にして、純白の豪奢な屋敷がそびえていた。ゆるやかなカーブをえがいている幅広の階段は、まるでどこかのステージのようだった。
周囲には、月明かりに照らされた背の高い針葉樹が所狭しとならんでおり、この屋敷と別の場所を繋ぐ道は、どこにも見あたらない。
上体を起こして座り込み、適当に体についた雪を払う。いらだたしげにため息をついて、ガイルは隼人の手を押し返し、ゆっくりと立ち上がった。
「しもやけ寸前だな。いや、もうなり始めか」
「うーん、すぐ帰るつもりだったから、手袋もつけなかったんだけどなぁ」
「ま、いい。とりあえずあのワケ分からん建物からも脱出できたんだし、とっとともとの世界に戻る方法を」
と、そこまで言ってガイルは口をつぐんだ。隼人はそんなガイルを、軽く首をかしげて見上げる。
「ガイルくん?」
「静かに」
う、ぞ、ぞ、ぞ・・・・
奇妙な音をたてながら、二人の正面に降り積もった雪が集まり始めていた。見えない何かが空中へ吸い上げるかのように、雪は円錐形を保ってどんどん巨大化していく。やがてそれは、ガイルの背丈を少し超えたくらいで止まった。
ただの子どもである隼人を背にかばい、ガイルは眼光鋭く雪の塔を睨みつける。
と、そこで唐突に声がした。
『やあやあ、今年のお客は二つの世界からとな! 珍しい、まぁいいだろう!』
「え、誰?」
『そちらの茶色の髪した坊ちゃん! 目の前にいる私がわからんのかね!』
ぞぞっ、と綺麗な円錐形を保っていた雪の一部が崩れた。鋭い先端は丸みを帯び、ぱっと一部の雪が何かに削り取られていく。最後、円錐形の雪の塔だったものは、まったく姿を変えその場でくるくると回り始めた。
『さぁーこのままでは格好がつかん! 来たまえ!』
先ほどと同じ、偉ぶった口調の割に小気味よく響くその声につられるように、針葉樹の森からひゅんひゅんと赤い何かが飛んできた。
「サンタの服だぁ!」
「さんた・・・・? って、あの石とか枝とかって、一体」
『ふふふ・・・・これで完璧だ!』
雪の塔の旋回はとまり、それはぴたりと隼人やガイルと向き合う形になった。ぱっと隼人の表情が輝く。
「すごいすごい! 三段重ねの、雪だるまサンタだー!」
白いファーで淵を覆われた、赤い三角帽子にコート、手袋、ヒイラギの葉のブローチで止めているマフラー。両腕と少々長めの鼻は針葉樹の枝で、目と口はまるで黒真珠のような輝きをもつ小石で形作られていた。
『うむ、茶色の髪の坊ちゃんはなかなか素直! 良いことだ! して、緑の髪の坊ちゃんはなぜそれほどまでに仏頂面なのかね!』
「お前がうさんくささの固まりだからに決まってんだろ」
ガイルは舌打ちをして、右手を左脇腹のあたりに泳がせた。これからは何があっても剣を手放すものかと、固く心に誓った瞬間だった。
『ふ、む・・・・そうか、自分はうさんくさいのか。これでも頑張って、坊ちゃんお嬢ちゃんたちに気に入られるようなデザインを考えたのだが』
白と赤のコントラストが絶妙な雪だるまサンタは、がくーっと前傾姿勢になった。そのままごろりと三段のうち一番上、つまり頭の部分が落ちる。
「あーっ、雪だるまサンタさん、元気出して。ほら、元に戻らないと、ちょっと怖いから」
『うむ! 心優しいのだな茶色の髪の坊ちゃん! では、君が今求めているものをあげよう! 何せ自分はサンタなのだからな!』
へ? と唐突な展開に隼人が目を白黒させていると、先ほど雪だるまが呼び寄せたサンタ装備と同じように、針葉樹の森から何かが隼人に向けて飛んできた。
思わず手をあげると、飛んできた何かはそのまま隼人の手にあたった。一度握りしめてから、隼人は目の前で手を開く。それは、今目の前にいる雪だるまサンタの目と口に使われている、綺麗な小石とまったく同じもの。
「あ・・・・」
『今、君が一番欲しいものは近々手に入るようだからな! 二番目のものを贈ろう! ・・・・で、これは自分の興味からの質問なのだが、なぜその石を?』
「えっ、えっと、綺麗だなって、思って・・・・妹にやったら、喜ぶかなーって」
『妹思い実に結構!!』
照れて顔をうつむけてしまった隼人から視線を外し、雪だるまサンタはぐるりとガイルに向き直った。瞬間、ずりっと帽子がずり落ちかける。
『緑の髪の坊ちゃん、君はなぜ、自分をそれほどまで強く睨むのか・・・・』
「自分で気付け」
素っ気なく言って、ガイルはそっぽを向く。しかし、すぐに雪だるまサンタの立ち直った声が響いた。
『ま、まぁよい! 素直ではなくともよい子はよい子! 帰りを待つ人もいることだし、なぁ!』
「・・・・よい子、だと? おい、お前」
ゆらん、と暗く光る青い瞳が、雪だるまサンタへ向けられる。
「適当なこと言ってんじゃねぇよ」
「ガイルくん?」
『・・・・適当なこと? 自分はいい加減に言ったつもりはない。よい子でなければ、ここには来れぬ』
雪だるまサンタはびょんっと大きく飛び跳ねて、その場でくるりと一回転をした。
直後、世界が白から蒼に変わった。
二人の少年は振り返る。屋敷の屋根の向こうには、驚くほど大きな、青い、白い、銀の月。
『緑の髪の坊ちゃん、君にはその手に余るほどとびっきりの、贈り物を』
「はぁ?」
『ふっふっふ、待つ人の元へ帰れば分かる! さて、今回も自分の仕事は終わった! そろそろ君たちも帰還の時! 異世界の聖夜を、それぞれ楽しみたまえ』
雪だるまサンタはにっこりと笑って、もう一度飛び跳ねた。そして、着地と同時にパッと弾けて消えてしまった。あのサンタの衣装や、木の枝も、どこにもない。
ガイルと隼人が呆然と雪だるまサンタのいた場所を見つめていると、ひらりと、蒼い世界に真っ白な欠片が降ってきた。白銀に輝く、冬の花。
「この上、また雪降るのかよ」
「でも、この景色、すっごい綺麗だよ」
月明かりに照らしだされた、狭間の世界。その幻想的な光景は、次第に、雪に覆われていく。
「あれ? ガイル、くん?」
「・・・・どうやら、もとの世界に帰されるらしいな。ったく、何でもかんでも唐突にやりやがって」
「ええ! じゃ、これってひょっとして小説とかアニメとかでお約束なお別れ!?」
「お約束ってなんだ。ま、そうだろうな。もともと異なる世界の人間同士、会うことなんか元々あり得ない。これからも会うことはないな。確実に」
「うわ、どうしよう、それならもっとあの建物の中でガイルくんといっぱい遊べばよかったー!」
「ハヤト、お前ってヤツは・・・・」
ガイルは深く深くため息をついて、視線をあげた。優しく宙を舞っていた雪の欠片はその量を増し、猛吹雪の時と変わらない。だが、刺すような冷たさ、痛みは感じられず、ただ視界だけが白に染まっていく。
隼人は、吹雪の切れ間から覗く若草色に向けて何度も、何度も手を振った。夢のような時間の終わり、不思議な贈り物を握りしめ、外見も雰囲気もまるきり自分と異なる少年へ。
「いい子にして、またここに来れたら、遊ぼうねー!」
「・・・・あーはいはい、っと」
何も、見えなくなる。
それでも二人はお互いに、ガイルは焦げ茶の、隼人は空色の瞳を、確かに見た。
不思議で、楽しかった、夢の聖夜。
がくがくと体を揺さぶられていることに気付くのに、さして時間はかからなかった。やたらとしつこく名前を呼ばれている。
ガイルは面倒くさそうに寝返りを打ち、むくりと起き上がった。
「ガイル! お前なんでこんなトコで寝てんだよ!? さすがのお前も風邪ひくぞオラ」
「・・・・お前の方が風邪引くんじゃないのか。ああ、そうか、よくあるなんとかは風邪をひかないって理論か」
「よーし、しつけ直してやるテメー」
びくりと口元を引きつらせて、珍しくマントを着ていないジャケット姿のステントラはガイルの額にデコピンをした。いつもやたらと白い彼の手は、指先に向けて徐々に赤くなっている。
「しもやけ?」
「そーだよっ! お前メモ見てなかったのかよ。宿に戻ったらもぬけの殻だし、町中かけずり回ってようやくココにそんな子どもが向かったって聞いて飛んできたら、この極寒の中実に満足そうな顔して寝てやがるし!」
「俺はまだ字が読めない。ていうかお前こそ何してたんだ。俺が宿の手伝いしてる間にいつの間にか消えて」
そこまで言って、ガイルは思わず身を引いた。ゴーグルの下の口が、にんまりと歪められたからだ。
「そろそろこの町も出るから、ちゃーんとツケ、払ってきたんだぜー? すごいだろ!」
「自慢することか精神年齢十歳未満。それぐらい当然だろ」
「・・・・俺はお前よか年下か」
「言動からするに。あと、いつものマント」
「いや、お前こそ気付けよ、体に巻いてんじゃん。いやー驚くくらい体冷えてたから、いっそいで宿屋に帰ろうにもなんか場が不安定で動くに動けなくてさ。・・・・ていうか、あれなんだったんだ? お前が起きた瞬間に不安定さが消えたんだけど」
「ああ、そりゃ・・・・」
そこまで言いかけて、ガイルは首をかしげた。自分は、なんと答えるべきなのだろう?
ステントラは目の前で、何か言いかけたまま自身の思考にはまりかけているガイルの頭を思い切り揺さぶった。すぐにガイルの視線がはっきりする。
「なにすんだ!」
「ま、いいや。とりあえず宿に戻って寝るぞー。ガイルもなんか俺みたいな顔色になっちまってるし」
「それは本気で嫌だな」
「うわお全力で否定されちゃったよ!?」
軽々と黒いマントに包まれているガイルを背負って、ステントラはとっとと寂れた教会を出た。
おんぶされるということ、そしてそれがステントラであるということに限りない不快感を覚えていたガイルだったが、冷え切った体は上手く動かない。舌打ちをして、ふと空を見上げた。
雲一つ無い、満天の星空が。
「うわ、さっきまでガンガン雪降ってたのに。すげー綺麗」
「雲まですっかりない・・・・」
それから、しばらくの間二人は半ば呆然と、教会の扉の前で幾億もの星々を見上げていた。
とても、暖かい。いや、温かいのかな。
そう思って、隼人はぱちりと目を開けた。
「はーくん!」
「・・・・あ、優ちゃん」
大きな瞳に、ショートカットが僅かに跳ねている髪型の少女の名を呼んで、隼人はへらっと笑みをこぼした。
「よかったー会えて。あれ、でも僕そういえばまだおうちに入ってなかったよね?」
「はーくん、お外に倒れてたんだよ。それ見て、おばあさまが・・・・」
「あ、そうだ。優ちゃん、元気になるお守り、ある?」
「え?」
少女、桃宮 優香はごしごしと潤む目元を拭いながら、布団の中で笑う隼人を見返した。
「未来が熱、出しちゃって。部屋にこもってつまんなそうだったし、すぐに治って欲しいなーって思って、そういや優ちゃんが、お守りくれたの思い出して」
「え、あ、あれは・・・・」
優香は一瞬すべての感情が抜け落ちてしまったかのような表情になったが、すぐにまたくしゃりと歪ませる。
「お守りは、ちゃんとあげる。でも、はーくんも風邪ひいちゃったら未来ちゃんすっごく悲しむよ! はーくんのお父さんとお母さんも、ついさっきここに来て大あわてだったんだから」
「うん、ごめんね」
「優ちゃん、隼人くんの具合・・・・あら、目が覚めたのね」
そこで、部屋のふすまがからりと開かれた。すっと静かに入ってきたのは、くせのある黒髪を簡単に結っている優香の母親だった。
優香の母は、優香がいるのとは反対側の隼人の枕元に膝をつき、そっとその白い手を隼人の額に当てた。ずいぶんと冷たかったが、今の隼人にはそれが心地よく感じられる。
「少し熱が出てきたわね。お社様の前で眠っちゃってたなんて、まったくもう」
「お母さん、あの、はーくん、未来ちゃんにお守りあげたいんだ、って」
「お守り?」
優香の言葉に、優香の母は僅かに目を大きくさせて隼人を見下ろす。すると、隼人はほんのり赤く染まっている顔で、むくりと布団から起き上がっていた。
「作んなきゃ」
「は、はーくんダメだよ。寝てて、はーくんのお父さんたちにはちゃんと」
「ううん、作りたいんだ。未来と約束したんだもん・・・・」
そう言って、隼人はぼんやりとした表情のまま、もぞもぞとジャケットのポケットをまさぐった。そこから取り出されたものたちを見て、二人は小首をかしげる。優香の母が、ポツリとつぶやいた。
「綺麗な石・・・・真珠みたいね。でも、こんなものどこで?」
隼人はそれに答えようとしたが、できなかった。この石を見ていると、なんだかとてもわくわくした気分になる。どこで手に入れたんだろう、何が、あったんだっけ?
「わかんない。でも作らせて。僕、全部使うもの買ってきたから!」
「作るって、一体何を・・・・あ、隼人くん、外に出ちゃ風邪ひどくなるわよ!」
しかし、隼人は優香の母が伸ばした手をかいくぐって、和室を飛び出した。その腕の中には、部屋の隅に置かれていた材料たち。そのうちのプラスチックの小さな透明ゴミ箱の中に、あの黒い石をごろごろと放り込む。
そのまま廊下を走りきって、隼人は手近な縁側から外へ飛び出した。靴下だけの足が、じんと痺れる。
「あ、雪」
はらはらと、暗い色の空から雪が降り始めてきていた。頬にそれが降りかかり、ふわりと溶けていく感覚に一度目を閉じる。なぜだか、ついさっきもこんな感覚を味わったような気がした。
二、三度頭を小さく横に振って、目を開いた隼人はその場にしゃがみ込み、積もっていた雪をかき集め始めた。
しばらくして、さあ完成というところで、耳慣れた声がいくつも、いくつも聞こえてきた。皆、自分の名を呼んでいる。心配させている。
「僕は、ここだよー!」
隼人は赤くしもやけた手を振って、縁側にあがった。何人かの下働きがそれを見つけて、大あわてで彼の手やら足やらを確認する。そこで、ふと彼が大事そうに抱えているものに目がいった。
「大葉くん、君、それ今作ってたの?」
「はい、妹にあげるんです。お兄ちゃんサンタなんです」
にぱ、と笑って、隼人はそれを慎重に掲げた。
透明なプラスチックのゴミ箱の中で、キラキラ光る黒い目の小さな小さな雪だるまが、幸せそうに笑っていた。
素材提供 :My new history